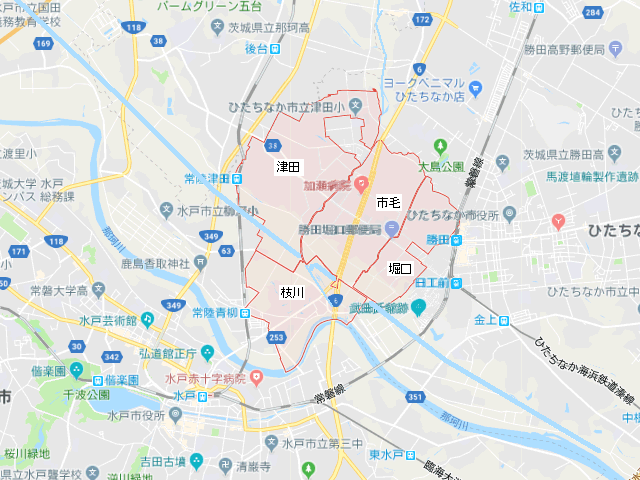柳田國男は『地名の研究』で「野」という地名について、次のようにいう。
山・岡・谷・沢・野・原などという語を下に持った地名は、たいたいに皆開発の以前からあったものと見てよかろうが、その中でも実例がことに多く、意味に著しい変遷があったらしいのは「野」という言葉であった。
これは漢語の野という字を宛てた結果、今では平板なる低地のようにも解せられているけれども、「ノ」は本来は支那にはやや珍しい地形で、実は訳字の選定のむつかしかるべき語であった。
白山の山彙を取り繰らした飛騨・越前の大野郡、美濃と加賀との旧大野郡、さては大分県の大野郡という地名を見ても察せられるように、また花合せ・骨牌の八月をノという人があるように、元は野(ノ)というのは山の裾野、緩傾斜の地帯を意味する日本語であった。
火山行動の最も敏活な、降水量の最も豊富なる島国でないと、見ることのできない奇抜な地形であり、これを制御して村を興し家を立てたのもまた一つのわが社会の特長であった。
野口、入野という類の大小の地名が、山深い高地にあるのもそのためで、これを現在の野の意味で解こうとすると不可解になるのである。
説得力のある説明である。
野とは、山の裾野や緩やかな丘陵など、地殻変動の大きく雨の多い日本に特有の地形であるという。
一方、漢字の「野」は、漢字源によると、
予は、□印の物を横に引きずらしたさまを示し、のびる意を含む。野は「里+音符予」で、横にのびた広い田畑、のはらのこと。
野は、ただ広がっている土地というのであって、未開の「原野」に近い意味なのであろう。漢語で「野生」「野獣」「野卑」などがある。「野(や)に下る」というが、この野をノと読んでは感じがでない。大陸では「広い土地」は平らであろうが、日本の野(の)は起伏のある土地もいう。
しかし、である。「原」についても同様に詳しく述べてもらいたかった。(電子本版で検索したが、野についてのような説明はないようである)。
藤原(ふぢわら、ふぢはら)などの地名が、「山深い高地にあるのもそのため」である、と言い切れるだけの説明がほしい。
しかしそれは、われわれ自身でやらねばならない。
そこで、まづ「漢字源」を見てみよう。
「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。
広い野原を意味するのは、原隰(げんしゅう)(泉の出る地)の意から。
また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)・頑(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。
日本でも、藤原や滝原 のハラは水源という意味なので、意味が近い。
「原隰(げんしゅう)(泉の出る地)」は、低湿地のことでもあり、葦原、芦原などは、その通りの場所である。
どうやら、和語のハラの元の意味も、漢字の「原」に近かったことになる。原の元の字形は「厡」であり、いかにも水源らしい字である。
さて広辞苑では、「原」とは「平らで広い土地。特に、耕作しない平地。野原。原野。万二(199)『埴安の御門の原に』」とある。説明では水源や湿地については触れていないが、用例文の「埴安」とは埴安の池のことである。
引用歌は万葉集巻二の長歌、柿本人麻呂による高市皇子への挽歌である。「埴安」とは、埴安の池という広大な池があったところで、この原と池の水源の詳細は不明だが、この御門は高市皇子の住居とされる。同じ歌に、他に2つの「原」が出てくる。
(1)「飛鳥の真神の原に、久方の天つ御門を畏くも定め給ひて」は、天武天皇の飛鳥浄御原宮を定めたこと。
(2)「不破山越えて、高麗剣 わざみが原の仮宮に」は、壬申の乱のとき、美濃国での天武天皇の仮宮。
(3)「万代に然しもあらむと、木綿花の栄ゆる時に、わご大君皇子の御門を、神宮に装ひ奉りて、使はしし御門の人も、白栲の麻衣着て、埴安の御門の原に、茜さす日のことごと」の「埴安の御門の原」が、高市の皇子の住居とされるが、「神宮に装ひ」という天皇クラスの表現が使われ、その(一時の)繁栄が歌われている。
こうした、天皇・皇子の御門や仮宮を建てる場所は、ただ広い土地だとか原野だとかいうのではなく、何か神聖な場所の意味が込められているように思えてならない。
天皇の宮の名前には、他に、橿原宮、軽の堺原宮、飛鳥川原宮、藤原宮など、「原」の文字はよく使われる。その場所を賛美しての名なのだろう。高天原の時代からなのだらうか。こうしてみると、広辞苑の「平らで広い土地。特に、耕作しない平地。野原。原野」のどれにも当らないような気がする。
※ ちなみに、他に、天皇の宮の名で多いのは、穴(片塩の浮穴宮、志賀の高穴穂の宮、穴門の豊浦の宮、石上の穴穂宮)、岡(葛城の高岡宮、軽の境岡宮、飛鳥岡本宮、長岡宮)がある。
そこで『古事記』を見てみる。
最初は「高天原」。解釈は難しい。
次に殺された火の神・迦具土神の体から八柱の神が生れ、その一柱に原山津見神。
つまり頭に正鹿山津見神。胸に、淤縢山津見神(おどやまつみのかみ)。腹に、奥山津見神。陰に、闇山津見神。この闇山津見神は、渓谷の神といわれる。
左の手に、志芸山津見神。右の手に、羽山津見神。
左の足に、原山津見神。右の足に、戸山津見神。
語義不明の名前も多いが、山や谷、その裾野のあたりまでの地形からの名のようであり、火山活動によって成った山のそれぞれの部分の神々のようでもある。
原山津見神は左足。原とは、山の裾のどこかをいうのだろう。
右手の羽山津見神は、山の端、あるいは尾根のあたりとすると、足は陰(谷)とつながる部分なので、尾根と尾根の間の土地、蛙の足でいうと水掻きに相当する部分ということになるだろうか。ここは扇状地であることが多い。谷から下る川によって原は左右に分割され、原山津見神と戸山津見神。群馬県の至仏山の東が戸倉、西が藤原であるのは偶然か(山で左右に分れる例だが)。
次に「葦原の中つ国」の「葦原」。これも難しい。
次に「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原(あはきはら)」で伊邪那伎神が、禊ぎをする。「阿波岐原」は、清い水が豊富な場所に違いない。やはり水源地であろう。それほど高くない滝があり、滝の水を浴びての禊ぎなのかもしれないが、後世では介添の巫女もあった。
次に、三貴紳の誕生。天照大神は「高天原を知らせ」、月読命は「夜の食国を知らせ」、須佐之男命は「海原を知らせ」とある。
「海原」とは、比喩的表現なのだろうか、それとも原にはもともと「海原」にふさわしい意味があるのだろうか。原は、夜の食国の「国」と同等のようにもとれる。
次に「天の安の河原」に八百万の神が集う。
河原とは、現在では、川の岸辺のことで、増水すれば水に覆われる。海原は、海辺のことではなく、常に広い海原のことである。河原の原と海原の原は同じではないのではないか。
大野晋『日本語の形成』によると、タミル語では、海を意味する paraval という言葉があり、天を意味する param もあり、原を意味する para もあり、それぞれ別の語とすれば日本語も同様なのかもしれない。さらに、parampu(台地)という言葉について「滝のある山の下の丘の斜面」というタミル語の成句らしき用例も載る。
同書では、日本語の原の意味としては次の用例を載せる。
「高平を原といふ 和名波良」(和名抄)
「車をむかひの山の前なるはらにやりて」(源氏 蜻蛉)
この源氏物語の「はら」は、原山津見神の生れたあたりに近い。和名抄の「高平」もほぼ同様で台地の意味だろうか。野との違いは、野が山裾の傾斜面、原は谷から続く川による堆積による平地ということかも。
4代懿徳天皇の「軽の境岡宮」と8代孝元天皇の「軽の境原宮」の場所がはっきりすれば、岡と原の違いもわかるかもしれない。
『日本国語大辞典』については「は」の項を含む1冊が見つからず、見つけ次第、追記する予定。(辞典を確認してみたが、原の語義の説明は小辞典並みの短いものであり、この辞典の悪い所である歴代諸氏による荒唐無稽の語源解釈を延々と掲載。この問題については全く役に立たない)