第二章 戌年参宮団
参宮案内
(昭和八年)
天地の神にぞ祈る、朝なぎの海のごとくに浪たたぬ世を。
畏きかな、昭和八年御題「朝海」の
大御歌であらせられる。非常時国難に対し奉る
大御心を拝察し奉るとき、臣子の分としてまことに恐懼に禁へぬ。この機会国土民族
挙り立ちて自覚更生に邁進し、以て
上御宸襟を案じ奉り、
下一身一家の安固を図らねばならぬ
秋である。
君臣一体の国体生活に精進し来れる日本民族は、恐れ多くも
上御一人の一挙手一投足が直ちに我等蒼生に反映するのが常であり、またあらねばならぬ。我が大里郡内神職氏子総代の有志相議りて、ここに自力更生を主眼とする国難打開の参宮会を企てた所以である。現下思想経済共に危機存亡の時歎に当面し、これが打開の一途は、実に精神更生を先駆とする経済更生あるのみと信ずるものである。我等の祈願もとより微力なりといへど、至誠奉公親しく天祖の御威霊に拝跪熱祷して、心からなる国民的真情を捧げたいと思ふ。
以下疎漏の起稿を渉漁して同行者と共に事前研究の資に充てたいとおもふ。(以下略)
睦会について
(昭和九年)
今年二月、会友二千の同志と共に国難打開の伊勢参宮を行ったが、めでたく奉仕を終へ、五月一日を卜して、四百名の人々が打ち揃うて楡山社頭に参集し、関係する五十九神社の神霊を招斎して、合同報賽の神事を執行し、同時に睦会といふ精神団体を結成した。さらに式後、神苑内に
荒筵を敷いて酒屋と団子屋とおでん屋の店を出して、非常時の園遊会といった一種変った直会式を挙げたところが、予期した通り、いかにも睦会らしい睦み振りを発揮して、一同、日の暮るるを知らで感激し合ったのであった。踊る、謡ふ、始めのうちは各班毎に固まり合ってゐたのが、遂には一団となり、一町十五ヶ村
(第三区・深谷地区が主体)にわたる人々が西も東もなく打ち解けて、呑み合ひ談り合った光景は、実に素晴らしい何とも形容の出来得ぬ親交振りであった。これを栞に毎年一回づつ呑み合って、いよいよ参宮気分を追憶しようなど心の底から誓ひ合ったことは、近頃珍しい情景であった。
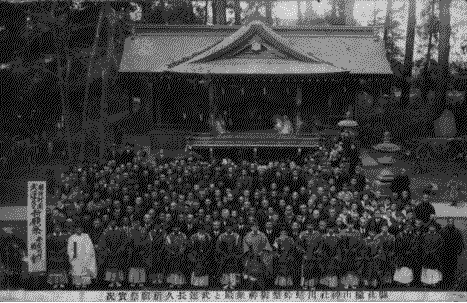
昔から参宮友だちは生涯忘れられないといふのを耳にしたが、全くそうかもしれぬ。しかしこの感激は、独り日本人なるが故に味はふことが出来得るもので、一度郷土を離れて旅行を共にしたときの親交は大概変りはないが、特別に情味あり感激あるものは、参宮友だちを措いて外に見ることができぬ。国民として最高の義務を尽くし得たといふ絶対の安心立命からする慶びに違ひない。さらにまたこの感激を永遠に追憶したいといふ考へから、一様に鎮守の境内に参宮記念の物を献り、金石にその氏名を留め、氏子としてまた皇国の民として、これを唯一の誇りとも考へてゐる。
かねて千家男爵
(出雲大社宮司)からお歌を頂戴したことがある。それは
末遠き家の栄をなすものは
本を忘れぬ心なりけり
といふのであった。本来の道明らけく、大義名分を確信する日本民族の情操には、昔も今も変りはない。村の鎮守を通してこそ初めて本当の参宮をした気持ちになれるし、村の鎮守を抜きにしたのでは幾度参宮してもそれは物真似としか思はれぬ。一行ことごとくそうした気分であったものから、参宮の傍ら、一部は高野山に親の足跡を訪ね、他の一部は我が武蔵国と国造を同じうする出雲大社に詣で、特に白衣上装門内参入の正式参拝やら、千家国造邸訪問など実行して帰ったのであった。
権利とか義務とかいった、理窟で固めた今の世相から暫時抜け出してみた今度の参宮会は、たしかに感謝といふ一大収穫があったことは、まことに
欣びに禁へぬ。感謝の二字を目標としてあらゆる生活場面にのぞむことが、やがては非常時打開の一端ではあるまいかといった、至極平凡な申合せが、即ち睦会結成の動機なり目的なりであった。各班毎に毎年一回は必ずその氏神鎮守の社頭に会談し、全会員もまた一年一回は一ヶ所に会合して、いつまでも追憶感激の情味に浸りたいといふ念願である。なほ時折修養、信仰、見学を目的とする旅行を重ねる仕事とした。
国難打開の参宮会
(昭和九年戌年)
二月二十日の
戌の日に出発した我等の参宮団は、一年がかりで結集した近来珍しい会友二千人といふ大仕掛の旅行団であったので、一行を三隊に分ち、三日間にわたって出発することとした。いづれも十輛つなぎの大列車で、六十班が各部屋に陣取って勇ましく乗り出した光景は、実に素晴らしい、全国的にも比類がなかったとのことであった。参宮線奈良線あたりで途中仲間同志の列車と列車とがすれちがったときなど、お互ひに無事を祈る万歳の喚声は、天にも響き渡っただらうし、一時は、参宮団といへば我等の一行が持ち切ったような感じもしたのである。
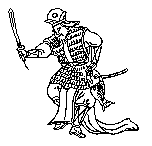
滞りなく参拝を終へ、神楽殿に特別
太々神楽を奉奏したときには、感極まって膚に粟する者さへあったとのことである。可憐な巫女舞や、雅びな
人長舞などは、いづれも拝観した
例しもあるが、今度はさらに「
陪臚」と「
納曽利」といふ二曲の舞楽が差し加へられたので、我等一行の為に特に奉奏せられたかのようにもとれたものから、一同の感激は一段のことであった。
ここに舞楽の説明を手短かにいふと、陪臚の舞は昔の戦の模様を象ったもので、推古帝の御代から今に伝へられてゐる古い舞楽である。舞人は金襴の鳥甲を冠り、赤色の
裲襠装束に太刀を佩き、鉾と盾とを持って四人して舞ふのである。昔から戦捷祈願などに用ゐられ、尚武の曲であったものから、八幡太郎義家などは、出陣毎にこの曲を奏して士気を鼓舞せられたといふことである。
また納曽利は一人舞で、龍の踊る状を象って作られたといはれ、舞人は恐ろしい仮面を冠り、萌黄色の裲襠装束を著け、右手に一尺ばかりのばちを持って舞ひ、すこぶる闊達の舞で、昔競馬の節会には必ずこの曲を奏して聖駕をお迎へしたといふことである。
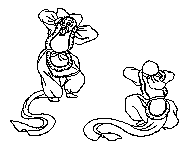
それから奈良、高野山、京阪地方の神社仏閣は申すまでもなく、一部は四国の金毘羅様から屋島の古戦場、岡山、宮島から、さらに下関の手前小郡廻りをして裏日本に出で、出雲を訪ね、我が武蔵国と国造を同じうする出雲大社に詣で、大国主神と鹿島・香取の神とが政権奉還の談判をせられた場所だといふ
稲佐の浜に案内人の説明を聞きながら、かつて日本海の大会戦もこのあたりの沖中であって砲声が手にとるように聞こえたなど聞かされたときは、暫時海上を見つめて感慨無量のものがあった。帰りに天の橋立に岩見重太郎(※)の敵討の場所だの探り、最後に善光寺のあま宮様まで拝んできた。
※岩見重太郎 秀吉の家臣で狒々退治などの説話に富む人物
いよいよ残務の整理を終へ、五月一日を卜して係員四百人を楡山社頭に集め、盛大なる合同報賽のお祭を執行し、さらに式後、神苑内に荒筵を敷いて、非常時の園遊会といった型の直会式を挙げ、併せて睦会といふ感謝の会を結成したのであった。
しかして一年がかりで二千人を動員した大運動の収穫が何であったかといへば、要するに感謝の二字に尽きてゐる。
権利とか義務で固めた温かみの薄い今の社会相から、たとへ暫しなりとも抜け出して、清い明るい懐かしい世界を見出だしたといふことはもっけの幸であり、世の中のあらゆる事物一切は感謝以外に何物もないとさへ思はれた。
(この項の挿絵は三省堂の大辞林から転載)
参宮記念石鳥居奉納碑誌
(昭和十一年大寄村戸森・雷電神社)
崇神の朝、司牧人神の詔を賜ひ、予て同殿共床に
斎かせ給へる親授の鏡劔を、
倭笠縫邑に遷祀し、更に
八十万神を祭りて、
天社国社神地神戸の制を定めたまひ、かくて
垂仁の朝に至り、皇女
倭姫命神器を奉して、伊勢の五十鈴の川上に皇大神宮御奉建の御事ありてより、神祇崇敬の国風
愈々昂揚し、国体の本義益々明徴を加ふ。由来国民一生の儀礼を仕奉れる伊勢参宮のこと、
亦故あるなり。
雷電神社氏子、常に敬神の念
惇く 参宮奉仕の者、歳と共に多きを加ふ。尊き
哉。今次同行
胥謀り、参宮報賽の先蹤に
倣ひて、社頭記念の石鳥居一基を
献りて、永く追憶感謝の慶を
偕にし、遠く報本反始の美績を伝ふ。
神威は高し
神路山、
愛みは深し五十鈴川( い すずがは)、
浄き
流の末遠く、汲む人々のまごころも、また滾々としてつきざるべし。
昭和十一年歳次丙子三月
県社楡山神社社司柳瀬禎治謹撰書
神徳讃仰碑
(昭和十年 八基村血洗島・諏訪神社)
東京帝国大学教授従三位勲二等工学博士渋沢元治題額
郷土の開宗
之を産土神といひ、部族の上祖これを氏神と云ふ。産子氏子は
汎く之を鎮守と称して、永く報本反始の誠を謁し、遠く尊王愛国の範を垂る。郷土に在りて礼をささぐる者、異郷に離れて義を忘れざるもの比々皆然り。諏訪神社氏子、殊に敬神の念惇く、神徳威霊赫々として六合に輝く。
宜なる
哉。子爵渋沢青淵先生、此地に生を享け、位は人爵を極め、身は輦轂の下に在りしも、常に古郷を訪ひ里人に親み、四時の祭事に仕へて懈怠なかりしことや、
洵に斯道の亀鑑にして、その感化の及ぶところ、老幼相率ゐて之に
倣ひ、崇祖愛郷の念湧然として興り、所在の献進また
滋きを加ふに至る。今次氏子胥謀りて往年経営の業跡を石文に勒して不朽に伝ふ。
亦次て聖代の美績といふべし。神は人の敬に依りて威を増し、人は神の徳に依りて運を添ふともいはる。余、不敏なれども、請はるるままに見聞の事実を誌して、奉讃の辞と為す。云爾
昭和十年歳次乙亥十月
県社楡山神社社司柳瀬禎治謹撰書
→
第三章 神社経営
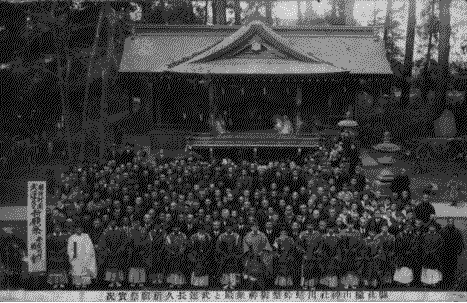 昔から参宮友だちは生涯忘れられないといふのを耳にしたが、全くそうかもしれぬ。しかしこの感激は、独り日本人なるが故に味はふことが出来得るもので、一度郷土を離れて旅行を共にしたときの親交は大概変りはないが、特別に情味あり感激あるものは、参宮友だちを措いて外に見ることができぬ。国民として最高の義務を尽くし得たといふ絶対の安心立命からする慶びに違ひない。さらにまたこの感激を永遠に追憶したいといふ考へから、一様に鎮守の境内に参宮記念の物を献り、金石にその氏名を留め、氏子としてまた皇国の民として、これを唯一の誇りとも考へてゐる。
昔から参宮友だちは生涯忘れられないといふのを耳にしたが、全くそうかもしれぬ。しかしこの感激は、独り日本人なるが故に味はふことが出来得るもので、一度郷土を離れて旅行を共にしたときの親交は大概変りはないが、特別に情味あり感激あるものは、参宮友だちを措いて外に見ることができぬ。国民として最高の義務を尽くし得たといふ絶対の安心立命からする慶びに違ひない。さらにまたこの感激を永遠に追憶したいといふ考へから、一様に鎮守の境内に参宮記念の物を献り、金石にその氏名を留め、氏子としてまた皇国の民として、これを唯一の誇りとも考へてゐる。 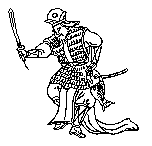 滞りなく参拝を終へ、神楽殿に特別
滞りなく参拝を終へ、神楽殿に特別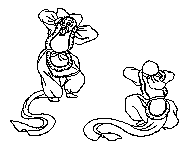 それから奈良、高野山、京阪地方の神社仏閣は申すまでもなく、一部は四国の金毘羅様から屋島の古戦場、岡山、宮島から、さらに下関の手前小郡廻りをして裏日本に出で、出雲を訪ね、我が武蔵国と国造を同じうする出雲大社に詣で、大国主神と鹿島・香取の神とが政権奉還の談判をせられた場所だといふ
それから奈良、高野山、京阪地方の神社仏閣は申すまでもなく、一部は四国の金毘羅様から屋島の古戦場、岡山、宮島から、さらに下関の手前小郡廻りをして裏日本に出で、出雲を訪ね、我が武蔵国と国造を同じうする出雲大社に詣で、大国主神と鹿島・香取の神とが政権奉還の談判をせられた場所だといふ